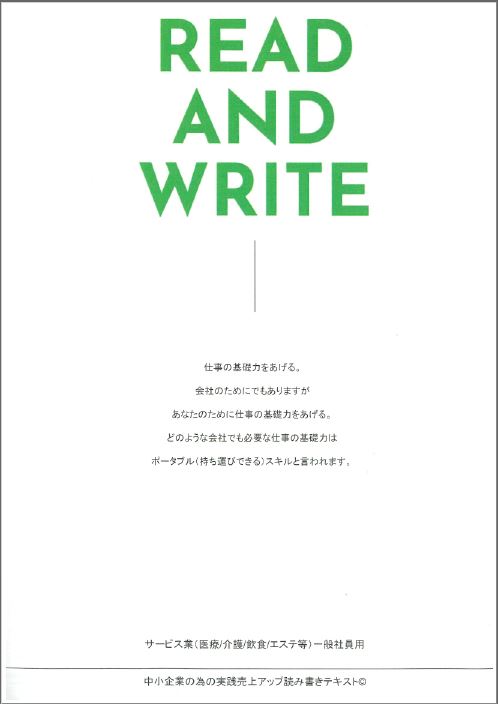第1回:「いい人が来ない」よりも怖い、“育てられない会社”の現実とは?
杉山 晃浩
1. はじめに — 採れないより、育てられないが深刻
「最近、本当に“いい人”が採れなくなった」――そんな声をよく耳にします。しかし、それ以上に深刻なのは、“せっかく入ってくれた人材が、育たない・辞めてしまう”という現実です。
中小企業白書2024では、企業の課題として「人手不足」と「人材育成の仕組み不足」が明確に示されています。採用はもちろん大切ですが、それ以上に問われるのは「育てる力」。
本シリーズでは、3回にわたって中小企業が抱える“人材育成の壁”に切り込み、最終的には「読み書き算盤」に通じる社会人基礎力教育の導入による突破口をご提案します。
2. データが示す現実:人手不足×教育体制の脆弱さ
まず注目すべきは、中小企業白書2024の以下のポイントです。
-
中小企業の業況は回復傾向にあるにもかかわらず、人手不足感はむしろ強まっている
-
「OJT」という名の放置型育成が多く、実際には教育体制が整っていない企業が大半
-
採用しても育たずに辞めてしまうという“負のループ”が慢性化
つまり、企業は「採用できない」と悩んでいるものの、その背景には「育てる仕組みがない」ことが根深く存在しているのです。
3. 素直でいい人材ほど、会社に“潰される”リスク
「本当に素直で、いい人だったんですけど、1年持たなかったですね…」
このような声、皆さんの周囲でもありませんか?これは決して本人の問題ではありません。実際には、
-
仕事の全体像がわからないまま丸投げされた
-
上司が忙しすぎて聞けない雰囲気だった
-
間違えても「なんでそんなこともできないの?」と否定された
といった背景があるケースが多いのです。
OJTという言葉に隠れて、“現場任せ”“気合いと根性頼み”になっていませんか?
4. 「教育の仕組み」はコストではなく投資
教育の仕組みをつくるには、たしかに一定の手間と時間、コストが必要です。しかし、それは「定着率の向上」「戦力化までの時間短縮」「社内の共通言語化」など、計り知れないリターンにつながります。
社労士として現場で多くの企業と接してきた中で、教育体制が整っている会社ほど、以下のような成果が出ています:
-
採用活動の際に“育てる自信”が伝わり、未経験者も応募してくる
-
育成担当者が明確で、業務が属人化しにくい
-
社員が「成長している実感」を得られ、モチベーションが高い
5. 次回予告:「社会人基礎力」とは何か?
では、具体的にどんな教育を社内で行えばよいのでしょうか?
次回は、社員の“成長の土台”となる「社会人基礎力」、つまり“読み・書き・算盤”に通じるスキルにフォーカスして、中小企業でもすぐに取り組める教育内容をご紹介します。
オフィススギヤマグループでは、毎日スタッフ全員が『READ AND WRITE』というテキストに取り組んでいます。
お気軽にお問合せください。