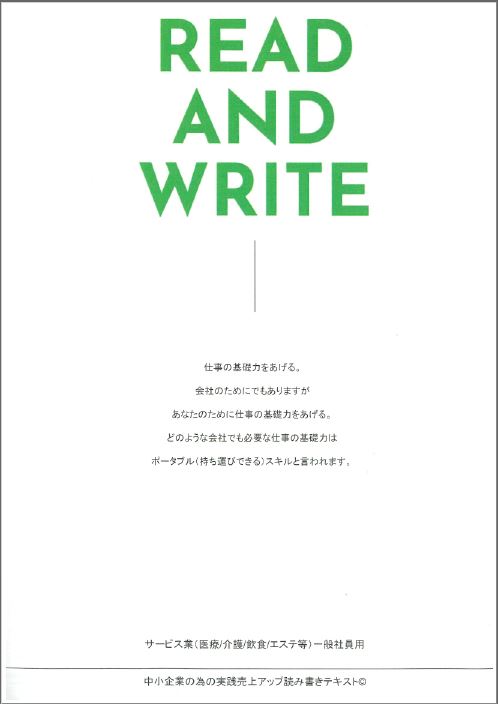第3回:社員が“自分のために”学びたくなる会社へ
杉山 晃浩
1. はじめに — 学びの動機は「自分の未来のため」
教育を受ける側の社員にとって、「これは自分の役に立つ」と思えるかどうかが最大のモチベーションになります。会社に言われたから、ではなく、「このスキルがあれば、他社でも通用する」「自分の市場価値が上がる」と感じられると、学びの質と量は飛躍的に向上します。
2. 社員が前向きに学ぶ組織には“共通点”がある
以下のような企業文化を持つ組織では、社員が自発的に学び、成長意欲を持ち続けています。
-
成長が評価される風土がある(結果だけでなくプロセスを見ている)
-
教える側も学ぶ文化がある(上司が学び続けている)
-
スキル習得が“キャリアの武器”として明確に提示されている
こうした環境づくりは、社労士としての支援テーマにも非常に親和性があります。
3. 社会人基礎力=“転職にも通用する力”と伝えることの効能
読み書き算盤、すなわち社会人基礎力は、職場だけでなく転職市場でも通用する普遍的なスキルです。企業がこのことを社内で明確に打ち出すと、以下のようなポジティブな連鎖が生まれます。
-
社員が「どうせ会社にしか通用しない教育」と思わず、自発的に学ぶ
-
教える側の責任意識も高まり、教育の質が上がる
-
結果として「辞めない」ではなく、「成長して残りたくなる」職場になる
4. 教育の“見える化”で、会社と社員の成長を同期させる
おすすめなのは「学びの可視化」です。
-
スキルマップの作成と共有
-
毎月の学習目標・達成記録の掲示
-
成長報告プレゼン(1人3分などのライトな場)
これにより、社員は自分の成長に自信を持ち、上司は育成状況を把握しやすくなります。
5. 社労士としての提案:人事評価制度や助成金と連動せよ
社員教育を促進するために、以下のような連携も有効です:
-
人事評価制度とスキルアップの連動(例:等級制度・目標管理制度との整合)
-
人材開発支援助成金等の活用によるコスト最小化
-
外部専門家との研修設計(講師、eラーニング、OJT支援など)
6. おわりに — 教育文化こそ、中小企業の未来を明るくする
「いい人が来ない」と嘆くよりも、「来てくれた人を育てる仕組みがあるかどうか」が問われる時代です。
寺子屋のように、基礎を繰り返し学び続ける文化を根付かせることで、社員は自ら学び、企業もまたその力で成長していく。そんな未来をつくるために、社労士が果たせる役割は大きいのです。
オフィススギヤマグループでも実際に効果が出ている『READ AND WRITE』のテキストを販売しています。
購入希望者はお気軽にご連絡ください。
電話番号 0985-36-1418